:2003.5.16:G.Gazzaniga「ドン・ジョヴァンニ」
 小劇場オペラの第10回公演として取り上げられた
このG.ガッツァニーガ作曲の「ドン・ジョヴァンニ」は、モーツアルトの同名の不朽の名作の陰に隠れているが、Amazonで検索すると、
CDが3種出ており、日本でも「モーツアルト劇場」による2度の公演記録もある。単独で歌われるような華麗なアリアはないが、
モーツアルトのものより喜歌劇の要素も強く、もう少し広く上演されても良いオペラではなかろうか。
台本(G.ベルターティ)の大筋は、モーツアルトのものと殆ど同じというより、逆に半年遅れで初演されたモーツアルトの曲の台本作家
(ダ・ポンテ)が、これを種本にしているようだ。ドン・ジョヴァンニ(T)、ドンナ・アンナ(S)、オッターヴィオ(T)、エルヴィラ(S)は、
同名で出ており、レポレッロ、ツェルリーナ、マゼットに対応するパスクァリエッロ(B)、マトゥリーナ(S)、ビアージョ(B)も登場する。
農民の婚礼の場などでは、曲まで似ていたようだ。音楽的には、ドン・ジョヴァンニがテノールの役になっている以外は、
登場人物の声域もほぼ同じである。また、エルヴィラ及びパスクァリエッロが一層重視されている。
なお、エルヴィラとマトゥリーナの口喧嘩のデュエットは、「フィガロの結婚」のスザンナとマルチェリーナのやりとりを髣髴させ、
面白かった。オーケストラは、弦中心の小編成のものであったが、木管・金管を代表して加わったオーボエとホルンが、
巧みに生かされていた。
小劇場オペラの第10回公演として取り上げられた
このG.ガッツァニーガ作曲の「ドン・ジョヴァンニ」は、モーツアルトの同名の不朽の名作の陰に隠れているが、Amazonで検索すると、
CDが3種出ており、日本でも「モーツアルト劇場」による2度の公演記録もある。単独で歌われるような華麗なアリアはないが、
モーツアルトのものより喜歌劇の要素も強く、もう少し広く上演されても良いオペラではなかろうか。
台本(G.ベルターティ)の大筋は、モーツアルトのものと殆ど同じというより、逆に半年遅れで初演されたモーツアルトの曲の台本作家
(ダ・ポンテ)が、これを種本にしているようだ。ドン・ジョヴァンニ(T)、ドンナ・アンナ(S)、オッターヴィオ(T)、エルヴィラ(S)は、
同名で出ており、レポレッロ、ツェルリーナ、マゼットに対応するパスクァリエッロ(B)、マトゥリーナ(S)、ビアージョ(B)も登場する。
農民の婚礼の場などでは、曲まで似ていたようだ。音楽的には、ドン・ジョヴァンニがテノールの役になっている以外は、
登場人物の声域もほぼ同じである。また、エルヴィラ及びパスクァリエッロが一層重視されている。
なお、エルヴィラとマトゥリーナの口喧嘩のデュエットは、「フィガロの結婚」のスザンナとマルチェリーナのやりとりを髣髴させ、
面白かった。オーケストラは、弦中心の小編成のものであったが、木管・金管を代表して加わったオーボエとホルンが、
巧みに生かされていた。
この日は、Bキャスト出演の日であったが、タイトルロールの上原正敏は、声を抑え気味にやわらかく歌い色事師の雰囲気を出そうとした
のかもしれないが、今ひとつ迫力不足を感じた。パスクァリエッロ役の志村文彦は、重厚な声と軽妙な演技でひときわ光っていた。禿げ頭、
赤鼻の扮装も良かった。エルヴィラの井上ゆかり、ビアージョの太田直樹、マトゥリーナの国光智子、オッターヴィオの塚田裕之は、
いずれも若々しく豊かな声を駆使しで好演であった。一方、演出(今井 伸昭)は、舞台中央部の開閉を巧みに利用して、
狭い舞台に奥行きを持たせたり、客席後部から登場した歌手を客席中央で歌わせたり、工夫の跡が見られ、
ドン・ジョヴァンニの地獄落ちの場面もまずまずであった。(2003.5.19)

目次に戻る
003.6.12:「欲望と言う名の電車」
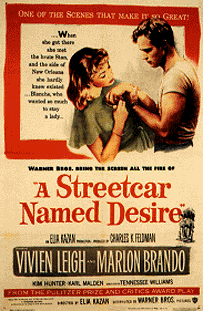 個人的には、「欲望と言う名の電車」と言う題名からは、まず、1950年代前半に公開されたエリア・カザン監督、マーロンブランド、
ヴィヴィアン・リー主演の名画が思い出され、作曲者のアンドレ・プレヴィンといえば、まずハリウッド映画が連想される。
このプレヴィンが、テネシー・ウイリアムズの原作に基づいて作曲し、1998年9月に初演されたのがこのオペラである。
「貸劇場公演」としての今公演(東京室内歌劇場主催・同劇場創立35周年記念特別公演)は、その日本初演となった。
このオペラについてネット上で調べると、欧米では、「21世紀後半の傑作として後世に残るであろう」とか、
「25年前のブリテンの”ヴェニスに死す”以来の最高の新作オペラである。」などと絶賛されているようなので大いに期待して出かけた。
プレヴィンの作風は、台詞入りのミュージカル風かなという予想に反し、プレヴィン自身が、「オペラにおける理想は、
ブリテン、バーバー、R.シュトラウスだ」と語っていように原作に忠実な会話劇となっている。古典的なアリアこそ無いが、
ブランチの独白場面等聞かせどころも多い。オーケストラも打楽器が活躍し、時には大きく盛り上がるが、歌の場面では音が適度に抑えられ、
お陰で歌詞(英語)もかなりよく聞き取れた。なお、原作の戯曲(和訳)
がネット上でも公開されている。
個人的には、「欲望と言う名の電車」と言う題名からは、まず、1950年代前半に公開されたエリア・カザン監督、マーロンブランド、
ヴィヴィアン・リー主演の名画が思い出され、作曲者のアンドレ・プレヴィンといえば、まずハリウッド映画が連想される。
このプレヴィンが、テネシー・ウイリアムズの原作に基づいて作曲し、1998年9月に初演されたのがこのオペラである。
「貸劇場公演」としての今公演(東京室内歌劇場主催・同劇場創立35周年記念特別公演)は、その日本初演となった。
このオペラについてネット上で調べると、欧米では、「21世紀後半の傑作として後世に残るであろう」とか、
「25年前のブリテンの”ヴェニスに死す”以来の最高の新作オペラである。」などと絶賛されているようなので大いに期待して出かけた。
プレヴィンの作風は、台詞入りのミュージカル風かなという予想に反し、プレヴィン自身が、「オペラにおける理想は、
ブリテン、バーバー、R.シュトラウスだ」と語っていように原作に忠実な会話劇となっている。古典的なアリアこそ無いが、
ブランチの独白場面等聞かせどころも多い。オーケストラも打楽器が活躍し、時には大きく盛り上がるが、歌の場面では音が適度に抑えられ、
お陰で歌詞(英語)もかなりよく聞き取れた。なお、原作の戯曲(和訳)
がネット上でも公開されている。
この日の公演は、ブランチ:釜洞祐子、ステラ:三縄みどり、スタンリー:宮本益光、という主役陣であったが、
歌も演技も大熱演であり、ドラマとしても大変面白かった。釜洞の演技は、映画でのヴィヴィアン・リーの強烈な演技と比べると
やや印象が薄いが、歌は良かった。宮本は、硬質で良く響く声が荒くれ男のスタンリーにあっており、好演であった。ステラの三縄は、
はじめて聞いたが、深みのある美声の持ち主で声量・歌唱力も充分であり、やはり好演であった。脇役では、ユーニスを歌った岩森が声、
演技とも役にぴったりで、異彩を放っていた。
演出は、回り舞台を巧く利用し、装置もニューオーリンズの雰囲気を出すため四隅にネオン塔を建てたりして、
簡素ながら良く工夫されていた。なお、このオペラが音楽的に大傑作かどうかは、まだ判断しきれないが、是非オリジナル・
キャストでのビデオ或いはCDで、聴き直して見たい。(2003.6.14)
目次に戻る
2003.6.15:「オテロ」
 オテロといえば、やはりNHK招聘の第二次イタリアオペラ(1959)での世紀のテノール、マリオ・デル・モナコ(写真)
主演の公演が思い出される。「黄金のトランペット」の異名で知られた彼の声は、確かに素晴らしかったが、大阪フェスティバルホール2Fの最後部で聴いたせいか、
意外に柔らかく響いたことを覚えている。
(その後10年位たって、彼が50歳代の時にコンサート会場の前席で聴いた時には、まさにトランペットの響きだと感じた。)
オテロといえば、やはりNHK招聘の第二次イタリアオペラ(1959)での世紀のテノール、マリオ・デル・モナコ(写真)
主演の公演が思い出される。「黄金のトランペット」の異名で知られた彼の声は、確かに素晴らしかったが、大阪フェスティバルホール2Fの最後部で聴いたせいか、
意外に柔らかく響いたことを覚えている。
(その後10年位たって、彼が50歳代の時にコンサート会場の前席で聴いた時には、まさにトランペットの響きだと感じた。)
今公演では、2000年9月の「トスカ」でスカルピアを好演したホアン・ポンスの出演する日を選んで出かけたが、彼を含めて歌手陣は、
適材適所で理想に近いものであった。タイトルロールは、ロシア出身のウラディーミル・ボガチョフが歌ったが、高音部はきわめて輝かしい一方、
リリックに歌い上げる部分も素晴らしかった。モナコやドミンゴとは一味違うが、猜疑心の強いオテロを良く表わしていた。
デズデーモナを歌ったイタリア出身のルチア・マッツァリーアは、体躯に比例して声も大きいが、高音から低音までむらのない美声で歌唱力も充分であった。
聴かせどころの有名な「柳の歌」から「アヴェ・マリア」の部分は、やはり素晴らしかった。スペイン出身のホアン・ポンスのイアーゴは、歌
、演技とともに体躯も堂々としており、充分に存在感を示した。カッシオを歌った吉田浩之も持ち前の伸びやかな美声を活かし、好演であった。
脇役陣も、エミーリアの手嶋真佐子等が好演した。
演出では、第一幕冒頭の戦闘の場面は、客席に向いた巨大な大砲及び兵士の適切な配置、背面スクリーンへ投影等によって大変リアルで迫力があった。
第四幕のデズデモーナの寝室でのデズデーモナの絞殺、オテロの自殺の場面もごく自然な動きであった。また、
第二幕、第三幕の巨大な石柱を配した広い空間は、重厚でなかなか良かった。菊池彦典指揮下の東フィルの響きも良かった。(2003.6.15)

目次に戻る

 <ジャン・コクトーオペラ二題>という副題の付いたこの室内オペラ公演は、小劇場での「貸劇場公演(主催:東京室内歌劇場)」
として行われた。共に初めて観るオペラであり強い関心をもって出かけたが、「声」はともかく、「哀れな水夫」は、
原作を読んでいないので比較は出来ないが、台本に無理があるように思われ、あまり楽しむことは出来なかった。まず、
モノオペラと呼ばれるプーランク(1899~1963、写真左)の「(人間の)声」は、昔どこかで見た記憶のあるメノッティの
「電話」同様ソプラノが電話を握って40分強独演するもので、伴奏もピアノだけの最も単純なオペラである。今回主役の「女」は、
日替わりで3人(2人は原語、1人は日本語)が歌ったが、この日は、高橋薫子が原語(フランス語)で歌った。高橋は、
上から下まで声が均質で大変美しい。今回もこの特質が充分に感じられ、好演であった。また小劇場なので、
後方の席でさえ間近に彼女の声が聞け、可憐な姿を見ることができたのありがたかった。舞台は、ほぼ予想通り、
ベッドと電話機だけのシンプルなものであったが、このオペラには、必要かつ充分であった。演出的には、「女」の心情が良く表れた
室内での立居振舞であったが、最後にベッドの上で電話のコードを首に巻いて死ぬ場面は、もう一工夫欲しかった。
<ジャン・コクトーオペラ二題>という副題の付いたこの室内オペラ公演は、小劇場での「貸劇場公演(主催:東京室内歌劇場)」
として行われた。共に初めて観るオペラであり強い関心をもって出かけたが、「声」はともかく、「哀れな水夫」は、
原作を読んでいないので比較は出来ないが、台本に無理があるように思われ、あまり楽しむことは出来なかった。まず、
モノオペラと呼ばれるプーランク(1899~1963、写真左)の「(人間の)声」は、昔どこかで見た記憶のあるメノッティの
「電話」同様ソプラノが電話を握って40分強独演するもので、伴奏もピアノだけの最も単純なオペラである。今回主役の「女」は、
日替わりで3人(2人は原語、1人は日本語)が歌ったが、この日は、高橋薫子が原語(フランス語)で歌った。高橋は、
上から下まで声が均質で大変美しい。今回もこの特質が充分に感じられ、好演であった。また小劇場なので、
後方の席でさえ間近に彼女の声が聞け、可憐な姿を見ることができたのありがたかった。舞台は、ほぼ予想通り、
ベッドと電話機だけのシンプルなものであったが、このオペラには、必要かつ充分であった。演出的には、「女」の心情が良く表れた
室内での立居振舞であったが、最後にベッドの上で電話のコードを首に巻いて死ぬ場面は、もう一工夫欲しかった。







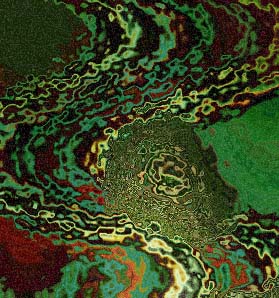 團伊玖磨の「建・TAKERU」、原 嘉壽子の
「罪と罰」に続く新国立劇場にとって3作目となるオペラ創作委嘱作品であり、もちろん今公演が世界初演である。原作は、
芥川賞作家の日野啓三、作曲は現代日本を代表する一柳慧である。今回は、原作も読まず、全く白紙の状態で劇場に出掛けたが、曲、
歌手、演出とも素晴らしく充分に楽しむことができた。曲は、打楽器や金管楽器の衝撃的な音を多用し、
効果的にドラマを盛り上げる一方、歌手にはそれぞれ聞かせどころを与えている。演出的には暗い場面を救い、
心理描写を補完するために男女のバレエ・ダンサーを登場させたのは面白いアイデアであった。
舞台は、宇宙船の内部を思わせる骨組みを中央に設置し、後方のスクリーンには宇宙から見た地球、月面歩行等の映像が写され、また、
題名の如くレーザ・ビームを含む光がコンピュータ制御で効果的に用いられた。 さらに、宇宙船の発射音や通信音、
カラスの鳴き声等の効果音も巧みに取り入れる一方、場面によっては、台詞のみの場面もあり、従来のオペラの概念を越えた作品
となっている。これは、東京文化会館が「舞台芸術創造フェスティバル」において、
ここ数年来模索している新しい舞台芸術形式の極致かとさえ思われた。
團伊玖磨の「建・TAKERU」、原 嘉壽子の
「罪と罰」に続く新国立劇場にとって3作目となるオペラ創作委嘱作品であり、もちろん今公演が世界初演である。原作は、
芥川賞作家の日野啓三、作曲は現代日本を代表する一柳慧である。今回は、原作も読まず、全く白紙の状態で劇場に出掛けたが、曲、
歌手、演出とも素晴らしく充分に楽しむことができた。曲は、打楽器や金管楽器の衝撃的な音を多用し、
効果的にドラマを盛り上げる一方、歌手にはそれぞれ聞かせどころを与えている。演出的には暗い場面を救い、
心理描写を補完するために男女のバレエ・ダンサーを登場させたのは面白いアイデアであった。
舞台は、宇宙船の内部を思わせる骨組みを中央に設置し、後方のスクリーンには宇宙から見た地球、月面歩行等の映像が写され、また、
題名の如くレーザ・ビームを含む光がコンピュータ制御で効果的に用いられた。 さらに、宇宙船の発射音や通信音、
カラスの鳴き声等の効果音も巧みに取り入れる一方、場面によっては、台詞のみの場面もあり、従来のオペラの概念を越えた作品
となっている。これは、東京文化会館が「舞台芸術創造フェスティバル」において、
ここ数年来模索している新しい舞台芸術形式の極致かとさえ思われた。 小劇場オペラ公演の第9弾としてハイドンの「無人島」がとり上げられた。ハイドンといえば、後期のいくつかの交響曲、弦楽四重奏曲、
トランペット協奏曲、チェロ協奏曲等が有名で、専ら器楽曲の作曲家として親しまれてきたが、音楽の友社の「オペラ辞典」によると、
18世紀においてはオペラやオラトリオなど大規模な声楽作品こそが作曲家の代表作であり、
器楽曲などは片手間の仕事の産物であったとのことである。ハイドン自身も履歴書の中で自分の代表作として、
3つのオペラ(「漁師の娘たち」、「突然の出会い」、「裏切られた真実」)やオラトリオ「トピアの帰還」)等
を挙げたこともあったそうだ。この「無人島」は、ブッファからセリアまで12曲あるハイドンのオペラの中では、
最もシリアスなものようであるが、ストーリーは、「無人島に置き去りにされたと勘違いした妻(とその妹)が13年ぶりに、
さらわれた海賊から解放された夫に再会する」と言う単純なものであり、出演者も男女2人ずつで、
合唱も無いきわめて小規模な室内オペラである。しかし、ハイドンらしい優雅な曲で、なかなか素晴らしいアリア
(第一幕のシルヴィアのアリア)もあり、結構楽しむことができた。
小劇場オペラ公演の第9弾としてハイドンの「無人島」がとり上げられた。ハイドンといえば、後期のいくつかの交響曲、弦楽四重奏曲、
トランペット協奏曲、チェロ協奏曲等が有名で、専ら器楽曲の作曲家として親しまれてきたが、音楽の友社の「オペラ辞典」によると、
18世紀においてはオペラやオラトリオなど大規模な声楽作品こそが作曲家の代表作であり、
器楽曲などは片手間の仕事の産物であったとのことである。ハイドン自身も履歴書の中で自分の代表作として、
3つのオペラ(「漁師の娘たち」、「突然の出会い」、「裏切られた真実」)やオラトリオ「トピアの帰還」)等
を挙げたこともあったそうだ。この「無人島」は、ブッファからセリアまで12曲あるハイドンのオペラの中では、
最もシリアスなものようであるが、ストーリーは、「無人島に置き去りにされたと勘違いした妻(とその妹)が13年ぶりに、
さらわれた海賊から解放された夫に再会する」と言う単純なものであり、出演者も男女2人ずつで、
合唱も無いきわめて小規模な室内オペラである。しかし、ハイドンらしい優雅な曲で、なかなか素晴らしいアリア
(第一幕のシルヴィアのアリア)もあり、結構楽しむことができた。





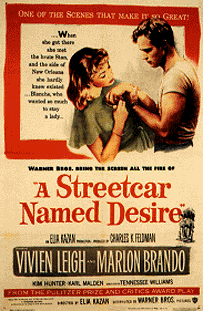 個人的には、「欲望と言う名の電車」と言う題名からは、まず、1950年代前半に公開されたエリア・カザン監督、マーロンブランド、
ヴィヴィアン・リー主演の名画が思い出され、作曲者のアンドレ・プレヴィンといえば、まずハリウッド映画が連想される。
このプレヴィンが、テネシー・ウイリアムズの原作に基づいて作曲し、1998年9月に初演されたのがこのオペラである。
「貸劇場公演」としての今公演(東京室内歌劇場主催・同劇場創立35周年記念特別公演)は、その日本初演となった。
このオペラについてネット上で調べると、欧米では、「21世紀後半の傑作として後世に残るであろう」とか、
「25年前のブリテンの”ヴェニスに死す”以来の最高の新作オペラである。」などと絶賛されているようなので大いに期待して出かけた。
プレヴィンの作風は、台詞入りのミュージカル風かなという予想に反し、プレヴィン自身が、「オペラにおける理想は、
ブリテン、バーバー、R.シュトラウスだ」と語っていように原作に忠実な会話劇となっている。古典的なアリアこそ無いが、
ブランチの独白場面等聞かせどころも多い。オーケストラも打楽器が活躍し、時には大きく盛り上がるが、歌の場面では音が適度に抑えられ、
お陰で歌詞(英語)もかなりよく聞き取れた。なお、
個人的には、「欲望と言う名の電車」と言う題名からは、まず、1950年代前半に公開されたエリア・カザン監督、マーロンブランド、
ヴィヴィアン・リー主演の名画が思い出され、作曲者のアンドレ・プレヴィンといえば、まずハリウッド映画が連想される。
このプレヴィンが、テネシー・ウイリアムズの原作に基づいて作曲し、1998年9月に初演されたのがこのオペラである。
「貸劇場公演」としての今公演(東京室内歌劇場主催・同劇場創立35周年記念特別公演)は、その日本初演となった。
このオペラについてネット上で調べると、欧米では、「21世紀後半の傑作として後世に残るであろう」とか、
「25年前のブリテンの”ヴェニスに死す”以来の最高の新作オペラである。」などと絶賛されているようなので大いに期待して出かけた。
プレヴィンの作風は、台詞入りのミュージカル風かなという予想に反し、プレヴィン自身が、「オペラにおける理想は、
ブリテン、バーバー、R.シュトラウスだ」と語っていように原作に忠実な会話劇となっている。古典的なアリアこそ無いが、
ブランチの独白場面等聞かせどころも多い。オーケストラも打楽器が活躍し、時には大きく盛り上がるが、歌の場面では音が適度に抑えられ、
お陰で歌詞(英語)もかなりよく聞き取れた。なお、
